チェレ・ジュンホーブ Cere junqóob カニのクスクス


学名:Cardisoma armatum
英名:レインボー(ランド)クラブ
チェレ・クラーブCere crabeとも言われる。
小粒の「チェレ」を使用する。
レインボー(ランド)クラブは、西アフリカの海岸に沿って、三角州や汽水域(淡水と海水が混じり合った塩分の少ない地帯)の水辺に巣を作る。夜行性で日中は砂地に掘った穴に隠れているが、暗くなると動き回る。半陸生。
トマトピューレをベースにしたソースに、レインボー・クラブ(オカガニの一種)を煮込んだクスクス。
セレール族の人達がよく食べる。セレール語で、サチュ・ファ・ハンブ(Sac fa ha qamb)と言う。ウォロフ語もセレール語も「カニのチェレ」と言う意味。


この料理を、大西洋の近くの海辺の村、Parmarinで作ってもらったが、料理に使うカニを浜辺に一緒に採りに行った。カニは浜辺の草を食べに来るのだが、逃げる時、穴に飛び込んで隠れ、砂で穴をすごい早さで塞いでしまう。その動作を見るのが面白くて、わざとカニを追って穴に追い込んでいたので、カニの収穫量はあまり多くなかった。(涙)
カニとチェレの味が思いもよらずマッチしているのには驚きだった。
チェレの代わりに普通の白米を使った、チェブ・ジュンホブもある。
チェレ・ヨホス Cere yoxos 牡蠣のクスクス

学名:Ostrea tulipa
セレール族の人達が好んで食べる。
小粒の「チェレ」を使用する。
セネガルでは、牡蠣は日本ほど高級感がない。肉を買うと高いので、牡蠣を肉の代用にしている。「貧乏人の食事」と言われている。




タマリンドの酸味、牡蠣の深みのある味、クスクスのほんわかとした雑穀の味。これらの味は噛めば噛むほど深い味わいとなって口の中に広がる。
因みに、チェブ・ヨホスは、お米ごはんと牡蠣の炊き込みご飯で。日本人の口に合ってとてもおいしい。
チェレ・パーニュ Cere paañ フネガイのクスクス

学名:Arca senilis
小粒の「チェレ」を使用する。
貝は、正確には、フネガイ科のオヤカタサルボウと言う。
ジョアル・ファディウ―ト島は、この貝殻でできている。


あさりの味に似ている。海の砂地に生息しているせいか、海の塩の味がする。

チェレ・ブージュ Cere buuj バカガイのクスクス

学名:Spisula nivea
ブージュBuujという「バカガイ」の仲間のクスクス。
小粒の「チェレ」を使用する。
チェレ・シンブ Cere simb カラスミのクスクス
シンブは黄色ボラの干物。ティシュタール(Tichtar)とも言う。
モリタニアから輸入して、サンルイの市場で売っている。

・チェレ・ハ―コ Cere haako
元々は、ギニアのフータ・ジャロンFouta Jalonのプル族のクスクス。
・チェレ・ターラーリ Cere Taalaali
魚のソースのクスクス。

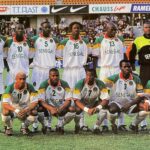


コメントを残す